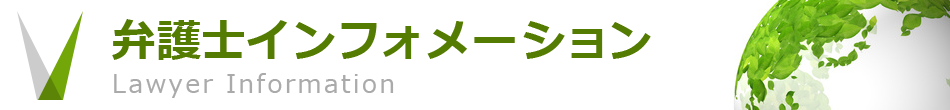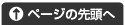弁護士インフォメーションには法律事務所関連の情報が満載
- » 弁護士関連情報 » 弁護士になるためには
例えば貸したお金が返ってこない、離婚に相手が応じてくれない、遺産分割でトラブルがある、損害賠償請求をしたい、本人同士での話し合いによる解決が困難となった場合、多くは裁判所へ訴訟や調停を申し出て解決を目指すことになるかと思います。
この各種裁判手続きに欠かせない存在として弁護士という資格があります。
弁護士をモチーフにしたドラマや小説も多く、その活動内容は広く周知されるものかと思います。
しかしどうやって弁護士になるのか、どれくらいの難関度なのか、司法制度とはそもそも何なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
近年日本の司法制度や法曹養成制度は頻繁に改正を繰り返しており、弁護士になるとしても何通りかの方法とルートがあります。
実は意外と複雑なのです。
つい数年前の大幅に改正されたばかりです。
弁護士になるためには司法試験に合格することが大前提ですが、司法試験を受験するためには受験要件があります。
司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了した者、または司法試験予備試験に合格した者、のどちらかの要件を満たしている必要があります。
改正前の試験では受験要件はありませんでしたが改正による条件が付けくわえられました。
また5年回のうちに3回しか受験できない、という回数の制限も儲けられました。
司法試験の合格率は3パーセント前後。
超難関の国家資格といえるでしょう。
また司法試験に合格すれば弁護士以外にも裁判官や検察官となる道も開けてきます。
また実例は少ないですが検察事務官から検事、弁護士を目指すというルートも存在します。
| 弁護士と裁判官 »