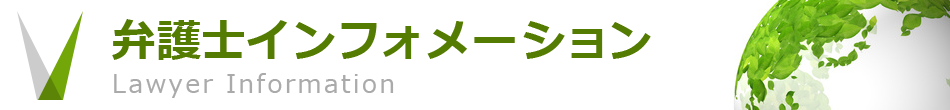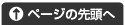弁護士インフォメーションには法律事務所関連の情報が満載
- » パワハラについて » パワハラ問題は他人事ではない!
セクハラ、といわれると職場においての度をこした異性間の接触や発言などのこと、ある程度どのようなものなのか多くの方が連想しやすいと思います。
ではセクハラと同じような意味合いを持つパワハラについてはどうでしょうか?
どのような発言や行為がパワハラに該当するのか、すぐに思いつく方というのは少ないのではないでしょうか。
近年厚生労働者において具体的なパワハラに関する行為について定義付けが行われました。
身体的な攻撃、つまり殴る蹴るの暴行傷害は当然許されるべき行為ではありません。
しかしパワハラは何も身体的な暴力だけではありません。
精神的な攻撃や人間関係からの切り離しなど、非常に加害者側からはわかりにくいものも、パワハラの定義に含まれています。
相手の尊厳や人格を否定する言動や、ムシや仲間外れ、度を越した仕事を押し付けたり、逆に仕事を与えない、プライベートなことに必要以上に立ち入る、などなど列挙すればキリがないほど、パワハラとなりえる行為は職場には数多く潜んでいるのです。
例えば終業後の飲み会参加への強要も相手が嫌がっていればパワハラに該当することになります。
またパワハラの関係性は何も上司と部下の間柄に限りません。
地位の上下に関わらず職場全体で起こりえるものになります。
自分は相手の上司ではないから多少の厳しい言動は許されるだろう、なんて事はあり得ません。
相手が深く傷ついていれば、それはパワハラと認定されてしまうこともあるのです。
パワハラは職場で働く一人一人の心掛けと企業側の努力でなくすことが出来る問題です。
企業側も積極的にこの問題に対して取り組みをみせるべきでしょう。
大手企業などでは外部講師を招き(社会保険労務士など)コンプライアンス研修を行ったり、独自の相談窓口を設置したりしています。
働きやすい職場、それがつまり生産力の向上につながるのです。