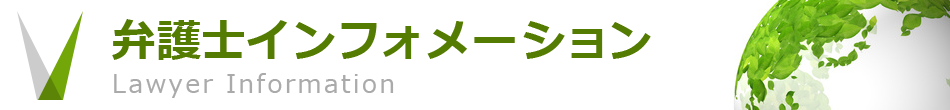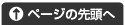弁護士インフォメーションには法律事務所関連の情報が満載
- » 企業法務(会社内でのトラブルなど)について » セクハラ防止に効果的な研修とは
そもそも当たり前ですがセクハラが起こらなければ問題は起きません。
セクハラを事前に防止する事こそが、最大の対策、になります。
セクハラを防止するためには最低限以下の三つが基本になります。
まず企業におけるセクハラに対する指針を明確にする
次に研修などを頻繁に行い社員や管理者の意識改革を行う
罰則規定の明確化、強化
特に社員の一人一人の意識改革を行うことはセクハラ予防対策において非常に重要です。
充実した研修を行うことによって、セクシャルハラスメントについての正しい理解と知識を持つことができます。
一人一人が強く意識することによって組織的な防止が可能になります。
しかし実際の現場では、毎年同じ研修テキストを使っていたり、研修のマンネリ化も目立ち始めています。
法務担当者はこれらの研修内容を充実させ、より関心興味を持ってもらえるような工夫を凝らす事を求められているのではないでしょうか。
ハラスメント問題が顕著化して10数年前後経過します。
セクハラやパワハラというものに対する世の中の浸透率は大分上がってきています。
どんな態度がセクハラでありパワハラ認定されるかというのは多くの方が理解出来ているのではないでしょうか。
そろそろ研修内容も次のステップへと進むべき時期といえるでしょう。
単なるセクハラとはパワハラとはどんなものか、ではなく、では実際に起こった例を元に意見を交わし合ったり、防止対策についてディスカッションしたり、ロールプレイングしたり、相談員を育成したり、今後は更に踏み込んだハラスメント対策を行う事が求められてくるのではないでしょうか。
各種ハラスメント対策は企業における義務です。
万が一問題が起こった際、企業側は対策をしていたから何も責任はありません、は通じません。
必ず責任を追及されます。
ハラスメント問題は個人間の問題ではありません。
企業の問題だという事を再確認しましょう。