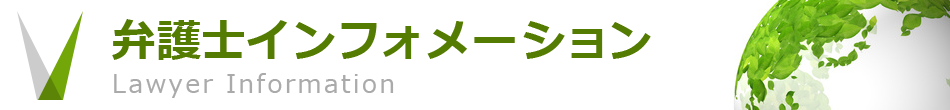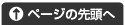弁護士インフォメーションには法律事務所関連の情報が満載
- » 企業法務(会社内でのトラブルなど)について » セクハラ研修の始め方!
ここ数年、権利意識の高まりの影響か、職場内のセクハラやパワハラに関する問題が急増しています。
実際労働局に寄せられる相談件数は増加していますし、訴訟件数もセクハラパワハラに関する事例が増えてきています。
そのため、少し前までは企業もあまり積極的にパワハラセクハラに対する対策を講じてきませんでしたが、近年ようやく本腰を入れて取り組むようになりました。
それは各種ハラスメント問題が企業に与えるダメージがどれだけ大きいかを痛感し始めたからといえるでしょう。
定期的にセクハラパワハラ防止月間や週間を設ける、など各企業におけるハラスメント対策は様々です。
実際の対策にも企業ごとに温度差があるといっていいでしょう。
研修を行うといっても、ひな形のテキストをダウンロードして、それの読み合わせだけを行っている企業もあれば、外部から講師を招いてディスカッション式の研修を行ったりする企業等、様々です。
研修の一番の目的は、社員にハラスメント問題の知識と危機感を持ってもらう事、です。
単なる読み合わせだけで果たしてそれが叶うでしょうか?
一応義務なので、セクハラパワハラ対策しています、研修しています、単なるポーズに何の意味もありません。
実際、ハラスメント問題が起こり、訴訟となった際には企業として対策を講じたか等も重要視されます。
特にセクハラの場合は被害者側に有利な判決が出やすい傾向にもありますので、企業側が背負う責任は小さなものではないでしょう。
効果的なセクハラパワハラ防止対策、その一環としての研修にはぜひ外部の研修やセミナーの活用をおすすめします。
社員一人一人が心の片隅にでも、セクハラパワハラに対する危機意識があれば、問題は確実に回避できるのです。
※経営者・総務担当者のためのセクハラ・パワハラ対策センターはこちら